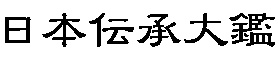青の洞門
【あおのどうもん】
菊池寛の小説『恩讐の彼方に』の舞台として有名な地である。
痴情のもつれから人を殺してしまった市九郎は、その後、己の罪深さを悟って出家し、了海と名乗って全国行脚の旅に出る。やがて豊後国の羅漢寺を参詣したが、その途中で、鎖一本を頼りに切り立った崖を通る難所で人が川に落ちて亡くなるところを目撃。そこで崖を掘削して道を造ることを一念発起する。20年近く掘り続ける了海の許へ若者が訪れる。それは父の敵と了海を探し求めた中川実之助であった。討ち取ろうとする実之助に対して、石工たちは洞門完成まで敵討ちを待ってもらうよう懇願。実之助はそれを受け入れるが、早く洞門を完成させようと、了海の作業を手伝うようになる。そして了海が掘り始めて21年目、遂に洞門は完成する。しかし実之助は、了海の慈悲の心に深く打たれ、憎しみを捨てて赦すのであった。
しかしながらこの小説の内容の主たる部分は菊池の創作であり、特に話の展開の軸となる敵討ちに関する事柄は一切創作である。
この青の洞門掘削に携わったのは、禅海という僧である。俗名は福原市九郎。江戸で両親が亡くなった後に仏門に入ったとされる。諸国を行脚している最中に羅漢寺を参詣し、その時にこの難所の話を聞き及び、開削を思い立ったという。また掘削の作業についても、禅海一人だけでおこなったわけではなく、むしろ普段は托鉢をおこない、それで得た銭で石工を雇い入れて作業に当たらせていたとされる。
それでも、享保20年(1735年)に洞門開削の大誓願を発してから30年もの年月を掛けて完成させる難事業であった。また周辺の村人の助けだけではなく、工事許可を与えた中津藩をはじめとする九州諸藩からの援助も受けての工事であった。トンネル部分144mを含む全長342mの洞門は、その後陸軍によって明治40年(1907年)に拡張工事がおこなわれ、禅海が開削したとされる部分の大半は新たに掘削された。しかし現在でも現役の道路として使用されており、トンネル部分にある明かり採り窓は禅海の時代のままであると言われている。




<用語解説>
◆『恩讐の彼方に』
大正8年(1919年)に発表された小説。
◆禅海
1691?-1774。親は越後高田藩の藩士。両親の死後出家して、諸国を回った。青の洞門完成後は、その地に留まったと思われる(洞門では通行料を徴収しており、最終的にその収入で生活してとも言われる)。なお羅漢寺のふもと(現在のリフト乗り場近く)に禅海堂という堂宇があり、禅海使用のノミなどが置かれている。
アクセス:大分県中津市本耶馬渓町樋田