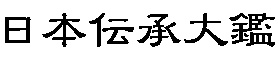白鳥神社(椿大明神)
【しらとりじんじゃ(つばきだいみょうじん)】
黒部川の河口付近に位置する荒俣地区は、かつては“村椿”さらに遡ると“玉椿”あるいは“玉椿千軒”と呼ばれていた。そしてその地区にある白鳥神社もかつては“椿大明神”の名で呼ばれていた(現在でも扁額には両方の名が記されている)。今でも境内には“玉椿”の名と共に椿の木が植えられている。まさに「椿の里」とも言えるこの地には、それにまつわる伝承が残されている。
かつて黒部川の良港として玉椿千軒と呼ばれ繁栄していた時代のこと。この地の長が京都へ赴いた時、その往復の道中で一人の武家と知り合い、同じ宿を取るほど懇意となった。そして別れ際、この武家は、自分は越後国の明光山の麓に棲む三越左衛門という齢1000歳の古狐であると正体を明かした。そして気が合うので、そのうちまた玉椿の地を訪問したいと告げた。長も共にいると楽しいので、その申し出を快諾したのである。
しばらくすると左衛門はたびたび玉椿に来るようになり、そのうち玉椿の裏山に心おきなく語り合える邸宅を建てた。その邸宅が出来た祝いを開き、懇意となった数名の者を招いたのである。宴に用意された酒肴はどれも見たこともないような珍味ばかりであったが、とりわけ左衛門が勧めたのは“人魚の肉”であった。しかし長をはじめ招かれた者は皆気味悪がって口にすることはなく、こっそりと懐中に入れて食べたふりをした。そして宴が終わると、銘々帰る途中でその肉を捨ててしまったのである。
後に左衛門は「人の寿命は短いので、もっと長らく語り合いたいと思って、是非とも人魚の肉を食べて長寿を保って欲しかったのだが。人間はやはり疑り深いものである」と言って、それ以来玉椿に姿を現すことはなくなったという。
ところが、一人だけ人魚の肉を家にまで持ち帰った者がいた。家で処分しようと思ったのだが、その家の娘が捨てる前に食べてしまった。娘はそれから嫁いで子を成した後も若いままの姿で、夫はもちろん子や孫にまで先立たれても歳を取る気配がなかった。やがて娘は剃髪して尼となり、手に椿の枝を持って諸国を遍歴した。そして“白比丘尼”とも“八百比丘尼”とも呼ばれるようになった尼は、800歳になる頃に若狭国の空印寺で入定したと伝わる。
この“玉椿出身”の八百比丘尼は回国の途中、能登国羽咋郡富来(現・志賀町富来)を訪れ、多くの椿の木を植えたという伝説も『能州名跡志』に残されている。またこの娘は玉椿で人魚の肉を食べたが、生まれは能登国鳳至郡繩又村(現・輪島市繩又町)であるとの伝承も残っている。


<用語解説>
◆八百比丘尼と椿
全国各地にある八百比丘尼伝説の1つのパターンとして「各所を回りつつ椿の木を植える」というものがある。特に北陸各県にその伝承が多いが、この地域の海岸沿いには椿の自生地が多くあり、その不思議さから八百比丘尼と結びつけられたのではないかと推察される。なお上記伝説地の“村椿”という名も、“群れ椿=椿の自生林”から来たものであるとの説もある。
◆『能州名跡志』
著者は文聾斎(太田頼資:?-1807)で、安永6年(1777年)の序が記されている。能登一国の地誌を著した書籍。
アクセス:富山県黒部市荒俣